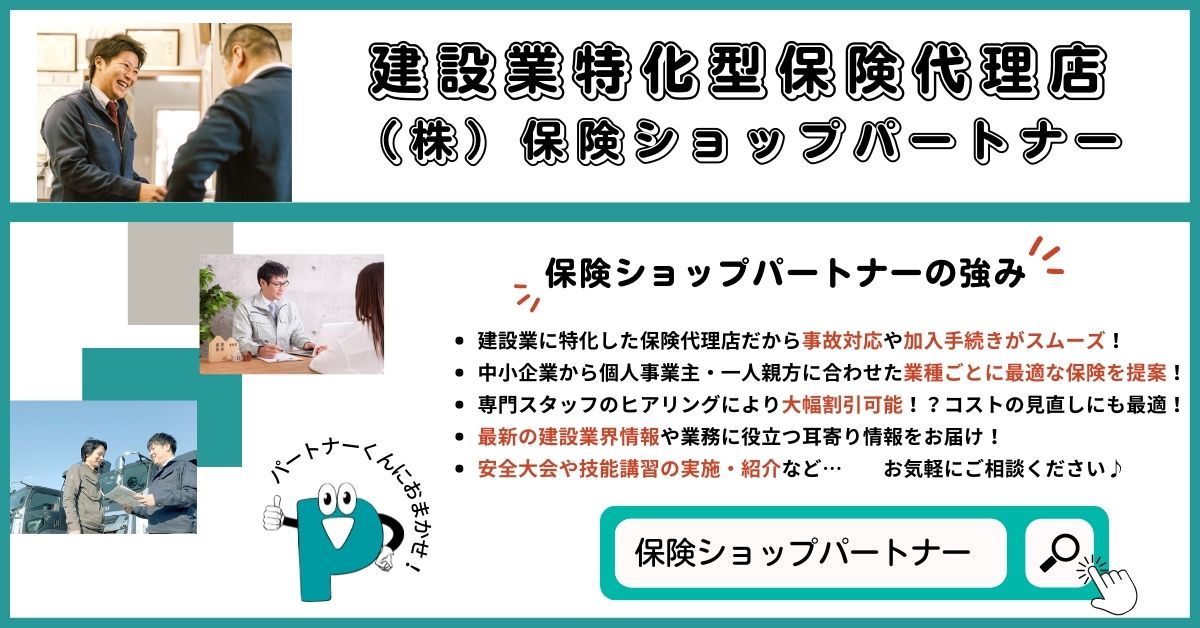職人に不可欠な「技術」と「心がまえ」とは?――建設現場職人のための「クラフツメンスクール」に行ってきました!その①
2021.07.16

建設業に関わる職人の方がたを対象とした、「クラフツメンスクール」という講習会をご存じでしょうか?
「各業種の職人の技術を、若い世代にしっかり継承しよう!」という目的で開催されるこのスクールは、2021年で7年めの開催。
通常の現場で「見て盗め!」とされる職人の技術や心がまえを、現地での実習からしっかり学ぶことができます。
当社も参加させていただき、現場職人のみなさまがどのような仕事を、どのような環境でされているのかを学ばせていただきました。
今回の記事では、2021年6月29日から開催されたクラフツメンスクールを受講して、学んだ知見をみなさまにお届けいたします。
「クラフツメンスクール」とは?

今回のクラフツメンスクールの大きなテーマは、「サイディング工事の流れ」。
サイディングとは、建物の外壁に使用する外壁材の一種。スクールでは5日間をとおして、建設物の外壁を完成させるための一連のプロセスや必要な知識、技術のポイントについてレクチャーされます。
外壁というのは、家を見て最初に目につく部分。せっかく家を建てても外壁が汚ければ、施工主はガッカリしてしまいます。
いわば外壁工事は、工事の「締め」ともいえる重要な仕事。その工程と技術のポイントを、さまざま学んでまいりました。
・「見て盗め」が基本!――技術を細かく教えてもらえない職人世界独特の慣習
そもそも、なぜクラフツメンスクールが開催されるようになったのか。その背景としては、「技術は見て盗め!」という建設現場ならではの慣習があります。
いざ職人見習いとしてデビューしても、実際の現場では、親方や先輩職人が仕事のイロハを手取り足取り教えてくれるわけではありません。
親方や先輩職人はそれぞれの仕事で忙しいので、若手職人の面倒を見てあげたくても、なかなか厳しい実情があります。
そのため、若手の見習い職人が作業を見よう見まねで作業を始めても、ほとんどの場合で失敗。結果として、ベテラン職人から厳しく怒鳴られることもしばしば。
若い職人の離職率が高いのは、このような仕事環境も大きな要因であり、建設業界の人手不足は年々深刻化しています。
・なぜ、保険代理店が技術講習に参加するのか?
今回のクラフツメンスクールには、当社の営業職の社員2名と、事故担当職の社員1名が参加させていただきました。
「なぜ、保険代理店の社員が職人のための講習に参加するのか?」と、疑問を抱くかたもいるでしょう。
当社が講習に参加する理由はズバリ、お客さまである現場職人のみなさまの世界を知るため。
私たちは、建設業の事故をリスクヘッジするあらゆる保険をご提供しておりますが、現場の実情を知らなければ、ベストな保険を提案することはできません。
職人のみなさまが、ふだんどのような仕事を・どのような環境で携わっているのか、その実情を知らなければ、事故のリスクを正しく把握することはできないと考えています。
お客さまである職人のみなさまのことを知ること。職人の方がたが現場でどのようなことに苦労し、どのような作業に危険が隠れているのかを知ること――それこそが、建設業向けの保険を提供するうえでの大切な第一歩なのです。
実際の講習現場から学んだ3つのこと

それでは、実際の講習内容を、参加者の感想とともにお届けしましょう!
・POINT1 実作業をとおしてベテラン職人がていねいに教えてくれる!
クラフツメンスクールは、全5日間のスケジュールでみっちり行なわれます。
初日の数時間は、まずは座学での講義。「現場でのコミュニケーション」「建設職人の仕事とは?」をテーマに、これからの5日間で学ぶサイディング工事の基礎知識を学びます。
その後はすぐに実習現場に移動!
作業場として家が1軒用意され、実作業をとおして講師の先生が道具の使い方や施工上のポイントをレクチャーしてくれます。
ちなみに、講師は長年の経験を持つベテランの職人ばかりです。
〈参加した当社社員の声〉
「5日間の講習のほとんどが実習で、各日朝8時から夕方18時まで現場での作業でした。ほかの参加者は25歳〜30歳くらいのかたが多く、外国人研修生のかたや外国人職人のかたも。『ふだんの現場では細かく教えてもらえないことを、このスクールでしっかり身につけたい』と、みな一様に学習意欲を高くもっていることがとても印象的でした」(法人営業部所属・男性)
・POINT2 失敗を糧に、確実に成長できる!
先述のとおり、建設現場というのは、仕事内容をていねいに教えられるわけではなく、「とりあえずやってみろ」と指示され、失敗すれば怒られるのが当たり前の世界です。
しかしクラフツメンスクールでは、初めに仕事の基本を教わり、実作業を行ないます。
ただし、参加者はひとつの作業を完了させるまで、いっさいアドバイスを与えられません。
たいていの参加者がなんらかの失敗をしますが、その失敗こそが成長の第一段階!
失敗した原因を探り、なぜ失敗したのか、どうすれば成功させられるのかを考えることで、初めて新しい技術を身につけることができるわけです。
〈参加した当社社員の声〉
「自分はそれまで営業職としてたくさんの現場職人のかたがたのお話を聞いてきましたが、実際に作業をしてみて、職人のみなさんがふだんどのような仕事をしているのか、その厳しさを体で知ることができました。ほかの参加者の職人さんがあるていどできることでも、自分はまったく手に負えず、現場のみなさんがすごい仕事をしているのだとつくづく実感。同時に、『失敗を恐れず、まずは自分の手で完了させてみよう』『失敗の原因を自分で見つけて、どうすれば成功できるのかを考えよう』という教えは、建設現場の仕事だけにいえることではなく、自分の通常の仕事にも通じる、重要な考え方であることを痛感しています」(法人営業部所属・男性)
・POINT3 技術のみならず、職人としての心がまえも身につく!
作業のテクニックだはもちろん、ベテラン職人である講師から、建築という仕事に携わるうえでの心がまえを学ぶことができます。
たとえば、「ハサミをしまわずに放置すると、日光で刃がダメになるから、つど腰の袋に戻す」「1ミリのズレが、完成後に大きな歪みの原因となる」「近隣住民を怖がらせないよう、現場では大声や怒鳴り声をあげない」など。
これはほんの一例ですが、すべては講師であるベテラン職人が長年現場で培ってきた経験から裏打ちされた言葉であり、だからこそ重みがあるのです。
〈参加した当社社員の声〉
「とくに心に残っているのが、挨拶の話です。挨拶が大切だとは充分わかっているつもりでしたし、それは現場の職人さんも同じかと思いますが、先生の話によると、頭でわかっていても意外とできていない人が多いのだとか。たとえば、『ここに荷物を置いていいですか?』などのちょっとした声がけができるだけで、現場の空気がぐっと改善されると聞きました。自分も建設現場を訪れる機会は多いのですが、意識的に挨拶や声がけをしなければという気持ちを改めています」(法人営業部所属・男性)
まとめ

今回の記事では、クラフツメンスクールに参加した感想と実際の受講内容をお届けしました。
本スクールの受講には費用がかかりますが、国からの助成金を活用することも可能です。
一般社団法人クラフツメンスクールから申請手続きを行なうことで、受講費310,910円のうち、206,400円が助成されます。
クラフツメンスクールと助成金の申請方法、活用事例について詳しくは、下記URLをご参照ください。
一般社団法人クラフツメンスクール:https://www.craftsmen-school.jp/
クラフツメンスクールの助成金活用事例:https://www.craftsmen-school.jp/casestudy/
本スクールで得た知識や知見は、日々大変な仕事に携わる建設業の職人のみなさまであれば充分ご存じのことかと思いますが、私たちにとってクラフツメンスクールは、これまで職人のみなさまからおうかがいしていたお話ーーたとえば、工事現場はつねに危険と隣り合わせの作業であること、技術の高さによって仕上がりが格段に違うことなどを、身をもって理解するための貴重な機会となりました。
私たちは、お客さまのことを深く知ることができたこの経験を活かし、みなさまの安全を守るためのベストな保険を提供すべく、ひきつづき精進してまいります。
続編「マナーひとつで、現場はここまで大きく変わる!――職人のための「クラフツメンスクール」に行ってきました・その②」も、ぜひあわせてお読みくださいませ!